斎藤茂吉 著による蛙作品を収集しています。
斎藤茂吉は、処女歌集『赤光』から遺稿歌集『つきかげ』まで、全18歌集、1万4千余首を詠んでいるそうです。
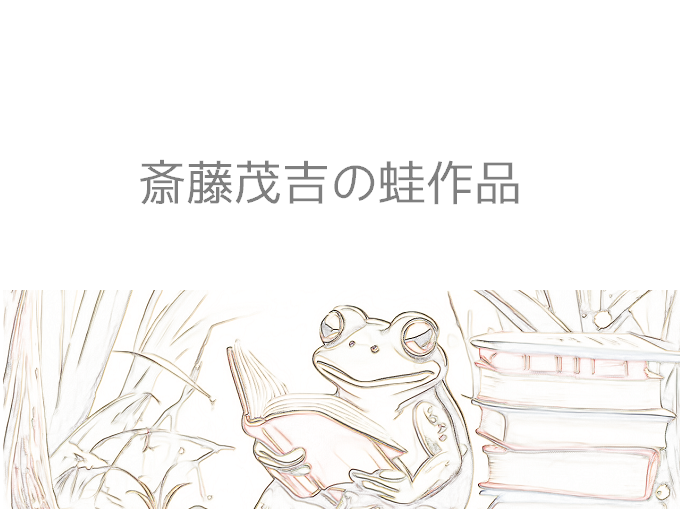
作者:斎藤茂吉(Wikipedia)
斎藤 茂吉(さいとう もきち、1882年(明治15年)5月14日 - 1953年(昭和28年)2月25日)は、日本の歌人、精神科医。
現在の山形県上山市で養蚕業も兼営する小地主の三男として生まれた。
大正から昭和前期にかけて活動した歌誌『アララギ』の中心人物。
第1歌集『改選 赤光』より(Wikipedia)
宵あさくひとり籠ればうらがなし雨蛙ひとつかいかいと鳴くも (12折に觸れて 明治四十二年)
ゆふ原の草かげ水にいのちいくる蛙はあはれ啼きたるかなや (4うめの雨 明治四十四年)
狂う院に寝てをれば夜は温るし我があぢかくに蟾蜍は啼きたり (7折々の歌 大正元年)
死に近き母の添寝のしんしんと遠田のかはづ天に聞ゆる (7死にたまふ母 其の二 大正二年)
第2歌集『あらたま』より(Wikipedia)
ことなくていま暮れかかる二月の夕はぬるし蟇いでにけり (6折々の歌 大正五年)
あまがへる鳴きこそいづれ照りとほる五月の小野の青きなかより (8雨蛙 大正五年)
かいかいと五月青野に鳴きいづる昼蛙こそあはれなりしか (8雨蛙 大正五年)
五月野の草のなみだちしづまりて光照りしがあまがへる鳴く (8雨蛙 大正五年)
五月の陽てれる草野にうらがなし青蛙ひとつ鳴きいでにけり (8雨蛙 大正五年)
さつき野の草のひかりに鳴く蛙こころがなしく空にひびけり (8雨蛙 大正五年)
青がへるひかりのなかになくこゑのひびき徹りて草野かなしき (8雨蛙 大正五年)
あをあをと五月の真日の照りかへる草野たまゆら蛙音にいづ (8雨蛙 大正五年)
五月野の浅茅をてらす日のひかり人こそ見えね青がへる鳴く (9五月野 大正五年)
行きずりに聞くとふものか五月野の青がへるこそかなしかりけれ (9五月野 大正五年)
さびしさに堪えるといはばたはやすし命みじかし青がへるのこゑ (9五月野 大正五年)
昼の野にこもりて鳴ける青蛙ほがらにとほるこゑのさびしさ (9五月野 大正五年)
青がへる日光のふる昼の野にほがらかに鳴けばましてかなしき (9五月野 大正五年)
くやしさに人なげくとき野の青さあまがへるこそ鳴きやみにけれ (9五月野 大正五年)
真日すみて天づたふとき五月野の動きて青しかへる音にいづ (9五月野 大正五年)
命あるものの悲しき真昼間の五月の草に雨蛙鳴く (9五月野 大正五年)
『あらたま』には、おたまじゃくしだけを詠んだ「蝌蚪」の小節もあります
第3歌集『つゆじも』より
ゆふぐれて浦上村をわが来ればかはづ鳴くなり谷に満ちつつ (大正七年漫吟 長崎著任後折にふれたる)
長崎のしづかなるみ寺に我が来し蟇が鳴けるかな外の池にて (大正九年五月四日 大光寺)
閨中の秘語を心平らかに聞くごとし町の夜なかに蛙鳴きたり (大正十年 帰京)
第4歌集『遠遊』より
見るかぎり青野ゆたかぶ起伏せば水の中にてひきがへる鳴く (維也納歌稿 其一 五月二十八日)
窓外に蛙のきこゆるは湖水に近く走るなるべし (伊太利亜の旅 六月二十日)
第5歌集『遍歴』は蛙作品なし。
第6歌集『ともしび』より
かぎろひの春山ごえの道のべに赤がへるひとつかくろひにけれ (摺針越抄 大正十四年)
青淵に蛙ひとつがいづこゆかぽたりと落ちてしづごころなし (木曽鞍馬渓 大正十四年)
むらがれる蛙のこゑす夜ふけて狂院にねむらざる人は居りつつ (雨 昭和二年)
うちわたす麦の畑のむかうより蛙のこゑはひびきて聞こゆ (雨 昭和二年)
郊外の病院に来て夜ふけぬたゐの蛙のこゑ減りにけり (C病棟 昭和三年)
第7歌集『たかはら』より
わがねむる家の近くに水足りて山の蛙は夜もすがら鳴く (野沢温泉即事 昭和五年)
南谷におもかげ遺る池の水時を過ぎたる蛙のこゑす (羽黒 昭和五年七月二十四日)
第8歌集『連山』は蛙作品なし。
第9歌集『石泉』より
伊豆の海に近くつづきし山中に蛙きこゆる夏になりたり (熱海小吟 昭和六年)
潮のおときこゆる山の小峡にて蛙のこゑはわれにまぢかに (熱海小吟 昭和六年)
第10歌集『白桃』より
わが眠る枕にちかく夜もすがら蛙鳴くなり春ふけむとす (厳島 昭和八年)
こよい一夜友と離れてみづに鳴く蛙のこゑを聞けばさびしも (厳島 昭和八年)
第11歌集『暁紅』、蛙作品なし。
第12歌集『寒雲』より
山のたをひとつ越え来て下谷に蛙のこゑす水ぬるまむぞ (選歌行 昭和十三年)
現身のわれが聞きつつ楽しかり数多の蛙とほりて鳴きぬ (御柱行 昭和十三年)
窓したの山がはに鳴く河鹿らを現かとおもひ否かとおもふ (布野 昭和十四年)
夜をこめて布野のはざまに鳴く蛙暁がたは稀にし鳴くも (布野 昭和十四年)
湧きいでてたまれる水のこもり處に蟇の蝌蚪生は安けし (歌碑行 昭和十四年)
やうやくに秋寂びむとすとおもほゆる此処の木立の雨蛙鳴く (續山荘日記 昭和十四年)
第13歌集『のぼり路』より
よもすがら蟇鳴く聞きて眠りしが朝あけてより蟇の卵見つ (加世田・伊作 昭和十四年)
第14歌集『霜』より
おもほえず此処にありける小峡より蛙のこゑす共に鳴きつつ (上ノ山小吟 昭和十七年)
青蛙高野槇より鳴きにけり蟋蟀よりもとほるこゑにて (午後 昭和十七年)
第15歌集『小園』より
むらぎもの悲しきまでにうちひびき蛙鳴きたつ峡のうへの空 (峡田の蛙 昭和十八年)
雨がへる朝木立より鳴くこゑす疾風はいまだ来むといはぬに (十八夜 昭和十八年)
赤がへるひとつ跳ねをりこのゆふべ降り来む雨をよろこぶらしも (強羅漫吟 昭和十九年)
この山の中に田あれやほがらほがら鳴ける蛙のこゑをし聞けば (疎開漫吟(一) 昭和二十年)
第16歌集『白き山』より
もろごゑに鳴ける蛙を夜もすがら聞きつつ病の癒えむ日近し (陸奥 昭和二十一年)
ここにして心しづかになりにけり松山の中に蛙が鳴きて (松山 昭和二十一年)
さびしくも雪ふるまへの山に鳴く蛙に射すや入日のひかり (寒土 昭和二十一年)
いたきまでかがやく春の日光に蛙がひとつ息づきてゐる (昼と夜 昭和二十二年)
冬眠より醒めし蛙が残雪のうへにのぼりて體を平ぶ (渡土獨吟 昭和二十二年)
穴いでし蛙が雪に反射する春の光を呑みつつゐたり (渡土獨吟 昭和二十二年)
河鹿鳴くおぼろけ川の水上にわが居るときに日はかたぶきぬ (胡桃の花 昭和二十二年)
小国川宮城ざかひゆ流れきて川瀬川瀬に河鹿鳴かしむ (猿羽根峠 昭和二十二年五月二十九日)
城山をくだり来りて川の瀬にあまたの河鹿聞けば楽しも (横手 昭和二十二年六月十四日)
いへいでて河鹿の聲をききたりしおぼろけ川にも今ぞ別るる (峡間田 昭和二十二年 茂吉送別歌会)
第17歌集『つきかげ』より
わが庭に鳴ける蛙を愛すれど肉眼をもてその蛙見ず (幸福 昭和二十四年)
第18歌集『万軍』より、蛙作品なし。
参考文献
関連場所
斎藤茂吉記念館
住所 :山形県上山市北町弁天1421
電話 :023-672-7227
休館日:毎週水曜日(祝日は翌日)、その他営業カレンダーによる
関連URL:公益財団法人 斎藤茂吉記念館

















